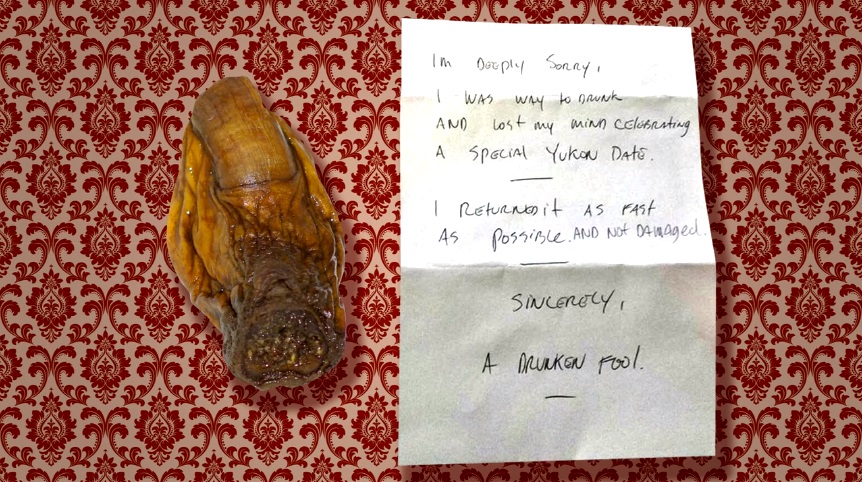アンドロイドか?人間か?議論を巻き起こした東京ゲームショウ“アンドロイド自動販売機”の舞台裏
Case:ソニー・インタラクティブエンタテインメント『Detroit Become Human』
話題になった、または今後話題になるであろう日本国内の広告・クリエイティブの事例の裏側を、案件を担当した方へのインタビューを通して明らかにしていく連載「BEHIND THE BUZZ」。
今回は、2018年発売予定のゲームソフト『Detroit Become Human』の東京ゲームショウブース展示について取り上げます。多数の出展者の中でも、ひときわ話題を集めたのが今回紹介する『Detroit Become Human』のアンドロイド展示ブースです。ショーケースの中に入っているアンドロイドについて、「本物のアンドロイドなのか人間なのか分からない」とTwitterで話題となり、一目見ようとブースには多くの人が押し寄せました。
ゲーム『Detroit Become Human』の舞台は、アンドロイドが人間と見分けがつかないほど進化した近未来のアメリカ。アンドロイドが広く普及した時代、意思を持つ変異体のアンドロイドが発生し、両者の対立を描くストーリーが展開されます。東京ゲームショウでは、本ゲームの近未来SFの世界観を現実世界で表現。ネット上で話題になっただけではなく、アンドロイドが当たり前にいる世界だからこそ現れる“人間の本性”という本ゲームの本質的テーマに迫る内容となりました。企画のコンセプトやブース展示の舞台裏、バズにつながった企画のポイントについて株式会社博報堂ケトル キャンペーンプランニングディレクター 清水佑介さん、プラナー 山澤雅之さんにお話を伺いました。
徹底した世界観の作りこみで、見た人の心をザワッとさせる
―『Detroit Become Human』東京ゲームショウ出展ブースのコンセプトを教えてください。
山澤:限られたスペースの中で、アンドロイドと人間の共存する世界というこのゲームのユニークネスを伝えようと考え、ゲーム内に登場するアンドロイドの自動販売機をモチーフに、アンドロイド役のモデルさん3人が入ったショーケースを展示しました。アンドロイドという設定ではありますが、人のかたちをしたものが自動販売機に入れられて売られている光景は、人身売買を目撃したような感覚になります。見た人の心がザワッとするようなショッキングなものを作ろうと考えて企画しました。
ショーケースの他にも、アンドロイド(を演じるモデル)にゲーム説明のVTRを再生してもらったり、試遊ブースまでお客様を案内してもらうことで、未来のアンドロイドが当たり前にいる世界を体験してもらえる仕掛けを施しています。

清水:ゲームの映像を流したり、ゲームを実際にプレイしてもらったりということはどこの展示でもやっていますし、ゲームの世界観を表現したロボットやモンスターなどの大規模な展示もあります。その中で、ゲームの世界の“生活の一部”をそのまま外へ持ってきて体験してもらうことは、他があまりやっていないことでした。このゲームは、設定が現実とかけ離れたファンタジーではなく、現実世界の未来の話なので、生活導線の中の自然な体験としての仕掛けができるのではないかと考えた結果です。
―クライアントからはどんなオファーがあったのですか?
清水:『Detroit Become Human』は海外の開発会社の作品ですし、完全な新規作品で、人気シリーズの続編というようなものでもないので、知名度はまだ高くありませんでした。誰もが知っているようなビッグタイトルの続編が同時に展示される中で、ゲームファンにまずは認識してもらい、少しでも多くの人にこのゲームの素晴らしさを知って欲しいという要望がありました。
―企画を立てる段階で、特に意識したことはありますか?
山澤:昨年「“キャバクラゲームショウ”やめませんか?」と訴えたブログが話題になりました。東京ゲームショウにいるイベントコンパニオンたちの肌の露出が激しく、ゲームそっちのけでコンパニオンの写真を撮りに来ている人が増えてしまった状況に問題提起をした記事でした。
そういった問題意識は私たちにもあり、お色気で人を集めるのではなく、このゲームのおもしろさを真正面に伝えようという意識が強かったです。
―来場者の間で話題になったことで、出展側の意識を変えることにもつながったようですね。
山澤:今回の企画が話題になったことを受けて、「入場料をとってお客様に来ていただくゲームショウのような場所では、その場にいないと見ることができないイベントならではの限定感を作り出していかなければならない」とか、「ファンを楽しませるコンテンツって、こういうものだ」といってくれるゲーム会社の人もいました。ゲームを作る人たちの気持ちに応えられたのはうれしかったですね。
リアリティを追求した演出が、アンドロイドだという錯覚を生んだ
―モデルさんをアンドロイドっぽくみせるために練習などはされたのですか?
清水:事前にトレーニングをして、動作の演出をしました。直線的な動きを意識してもらったり、レスポンスをわずかに遅らせたりすることでアンドロイドらしさを出すことを目指しました。動いて、ピタッと止まり、また元の位置に戻ることで機械っぽい動きを出しています。他にも、肌の温かみを出さないよう、べったり作り物っぽく見えるメイクをしてもらいました。
山澤:実際のゲームの中のアンドロイドは、実はもっとスムーズに人間と同じように動きます。ただ、現代において、アンドロイド役の人間が人間らしい動きをしたら、人間になってしまうので(笑)、あえてゲーム以上にちょっと違和感のある動きを演出しました。その演出が“現代の人が認識するアンドロイドの動き”にマッチしていたんだと思います。

―Twitter上では、アンドロイドだと思っていた人が多数いましたが、実際に来ていた人はどうとらえていたのでしょうか。
山澤:アンドロイドだと認識している人、人間だと認識している人、半々だったと思います。マネキンに当てるようなライティングの仕方、メイク、動き、ショーケースのスクリーンを挟んでの視認など様々な要因が絡み合って、錯覚を生んだのだと思います。
―現場でアンドロイドなのか人間なのか聞いてくる人もいたと思いますが、どう答えていたのですか?
山澤:世界観を壊さないよう、「サイバーライフ社(ゲームの中で出てくる架空の会社)のアンドロイドです」という答えで統一していました。
ネット上での話題化によって無名タイトルが「フューチャー賞」受賞
―Twitterで14万リツイートされるなど、かなり話題になりましたが、最初から話題化させることを想定して作っていたのですか?
清水:「人が売られているというショッキングな体験」が狙いで、そのショッキング性をより強めるためにリアリティを追求したというのが本当のところです。正直、アンドロイドだと思い込ませるのが目的ではありませんでした。もちろん話題化は狙っていましたが、アンドロイドだと誤解する人がこんなにも多いとは思っていませんでした。
―ブースにはたくさんの人が集まったのではないでしょうか。
山澤:周りのブースに迷惑をかけてしまうほどたくさんの人が集まってくれました。動画や写真のシェア数は、数あるブース展示の中でも『Detroit Become Human』が一番多かったと思います。SNSやネット掲示板でも、アンドロイドなのか人間なのかで盛り上がり、いろんなところで議論が巻き起こっていました。
清水:イベント開催中、ずっと人が絶えなかったです。2日目以降は、ネットで情報が拡散したことで、わざわざこのブースを見るために東京ゲームショウまで来たという人も多かったです。ネット上の情報拡散によって、リアルの場に人を呼ぶ好循環ができました。

―クライアントからの反応はいかがでしたか?
清水:『Detroit Become Human』を開発しているフランスのQuantic Dream(クアンティック・ドリーム)という会社は、コアなゲームファンの間では評判がよいのですが、このタイトルに期待しているファンはまだそうした限られた人たちでした。ほとんどの人は認知していないという状況だったのですが、今回のゲームショウで話題になったことで、クライアントにも非常に喜んでいただきました。当日はQuantic Dreamの社長も来場していたのですが、日本のプロモーションの力の入れように大変感激していました。
―ゲームのヒットにもつながりそうですね。
清水:たくさんの人を集めたことで、ゲームショウに出展した未発売のタイトルの中から来場者が投票し、投票上位の中からさらに選考委員がピックアップする「フューチャー賞」という賞をいただきました。ビッグタイトルと並んでの受賞で、海外の新規タイトルが獲得するのは異例のことです。この賞を取ることは、コミュニケーション戦略において、重要なステップだったので、受賞できてホッとしています。
あえて配信しないことで、実際に確かめたい欲をかきたてる
―バズにつながったポイントは何だと思いますか。
山澤:企画の内容と時代性がぴったり合っていたというのが大きいと思います。実写にしか見えない3DCGの女子高生の動画が話題になったり、マツコロイドやテツコロイドが登場したりするなど、見る人の頭の片隅にテクノロジーへの期待や、今の技術の予備知識があり、それらとうまくリンクして錯覚を生んだのだと思います。
清水:時代性とマッチしたこと、人間が演じているのか本物のアンドロイドなのかという議論が起こったこと、もうひとつは、実際に来てみないと確認できないことがポイントになったと思います。会場から映像配信をすれば、より多くの人に届けられますが、あえてそうしなかったことで、リアルイベントとしての成功につながりました。

―SNS上やイベントに集まってくれた方の反応などで、印象に残っているものはありますか?
清水:体験してくれた人がTwitterで「実際にこんな風にアンドロイドが売られる社会になったら、こうやって眺めたり、アンドロイドの女の子にいたずらしたりする人が普通に出てくるんだろうな」といったつぶやきや、「アンドロイドにわらわら集まっている人間をはたから見ることがこのゲームの世界では普通に起こっていることなんだろうな」といったことを書いてくれた人がいました。
人間のイベントコンパニオンだったら、体に触ることはしないのに、アンドロイドだったらそれをしてもいいというマインドがはたらくのが人間です。そうした、近い将来多くの人が感じるであろう違和感や疑問を、現実世界に生み出す表現ができたのではないかと思います。
本来、このゲームはアンドロイドを操作して物語を進めていくゲームです。アンドロイドがショーケースに入っているのは、ゲームの要素としては風景の一部でしかありません。しかし、その風景を通して、ゲームの世界を感じ取ってくれた方がいたことは、とてもうれしいことでした。

清水:今回、アンドロイドというフックで話題にしてもらうことができましたが、ゲームとしてはもっと伝えていかなければならないことがたくさんあります。ゲームの世界を現実世界に持ってくることによって、たくさんの人にこのタイトルの面白さや奥深さを擬似体験してもらうことができると分かりました。こういったアプローチのプロモーションにはさらにチャレンジしたいと思っています。

(写真左から)株式会社博報堂ケトル プラナー 山澤雅之さん、キャンペーンプランニングディレクター 清水佑介さん
 記事をブックマークする
記事をブックマーク済み
記事をブックマークする
記事をブックマーク済み
1